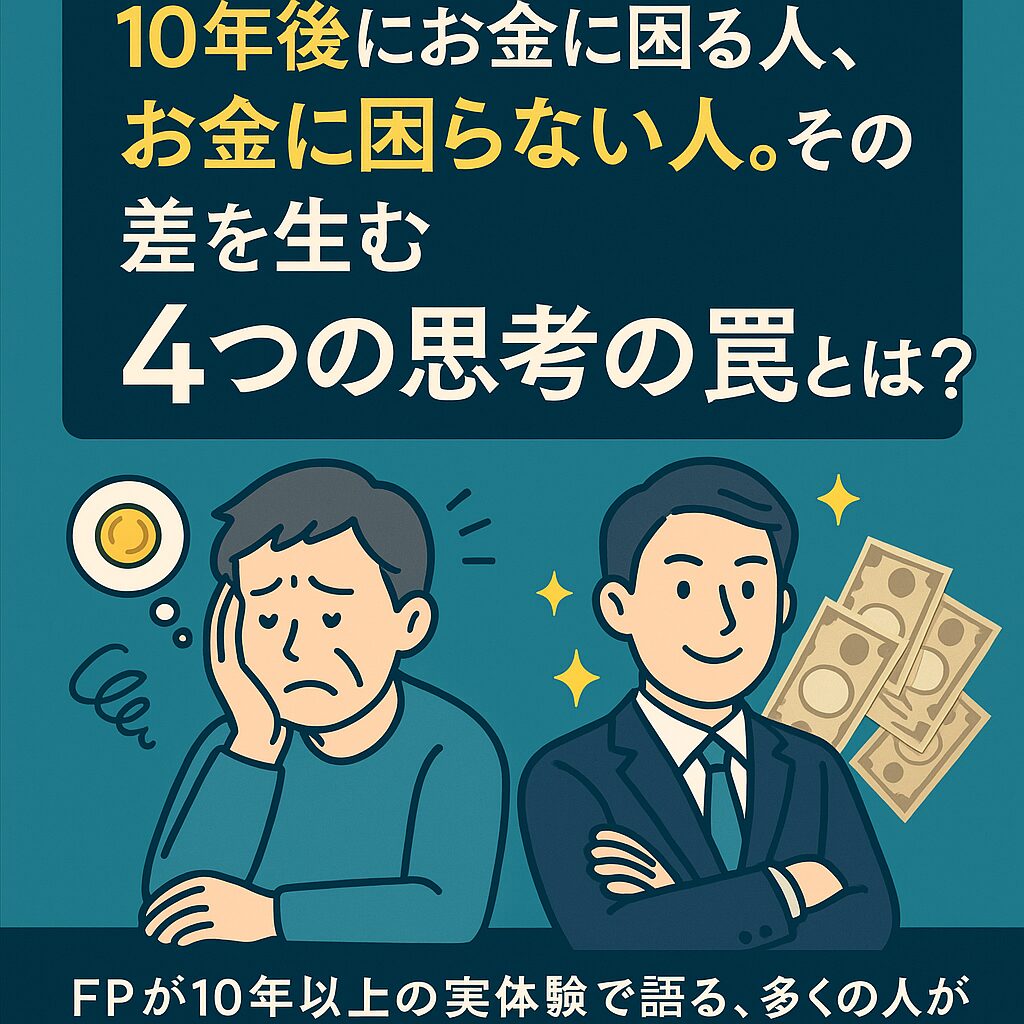FPが10年以上の実体験で語る、多くの人がハマる「非合理的な判断」の正体と、その具体的な対策
「将来のために貯金しなきゃ、と思いつつ、つい無駄遣いしてしまう…」
「頭では分かっているのに、なぜか損する選択ばかりしてしまう…」
そんな風に、自分の「非合理的な判断」に悩んでいませんか?
実はそれ、あなたの意志が弱いからではありません。人間の脳に元々備わっている「思考のクセ」が原因なのです。
10年以上、お金のコンサルティングをしてきた私の経験上、お金に困ってしまう人の多くが、知らず知らずのうちにこの「思考の罠」にハマっています。
この記事では、ノーベル賞受賞者も研究する「行動経済学」の観点から、多くの人がお金の判断を誤る根本的な理由と、特に注意すべき4つの強力な心理的バイアスを、具体的な事例と共に徹底解説します。
この記事を読めば、あなた自身の思考のクセを理解し、それを逆手にとって「お金に困らない」合理的な選択ができるようになります。
この記事の内容は、以下の動画でも詳しく解説しています!
前提:なぜ私たちは「非合理的」な判断をしてしまうのか?
具体的な罠の話に入る前に、そもそもなぜ人間は合理的な判断が苦手なのか、その根本的な理由を3つ理解しておきましょう。
- 脳が「超」省エネ思考だから:人間の脳は、生存に不要な思考を極力避けるように設計されています。考えることはカロリーを大量に消費するため、本能的に「考えない」ことを選んでしまうのです。
- 「感情」が判断を邪魔するから:「嫌いな営業マンだけど、提案内容は一番良い…」という状況で、合理的に一番良い提案を選べる人は少数派です。好き嫌いといった感情が、合理的な判断を曇らせます。
- 判断するための「知識」がないから:メリット・デメリットを比較検討するには、その土台となる知識が不可欠です。知識がなければ、そもそも合理的な判断はできません。
これらの人間の特性が、これから紹介する「思考の罠」を生み出す土壌となっているのです。
お金に困る人がハマる「4つの思考の罠」と具体的な対策
それでは、10年以上の相談現場で見てきた、特に多くの人がハマりがちな4つの罠を、行動経済学の理論と共に見ていきましょう。
罠1:現状維持を好む「デフォルト効果」
「人は、よく考えずにただ初期設定に従うだけ」。これは2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー氏が指摘した、人間の強力な性質です。
スーパーで30種類のヨーグルトを前にした時、成分やコスパを全部比較して買う人はいませんよね?
ほとんどの人は「人気No.1」や「脂肪ゼロ」といった分かりやすい表示(=初期設定)を見て、「これでいいか」と買ってしまうはずです。これが思考をショートカットするデフォルト効果です。
【実例】企業型確定拠出年金(DC)の加入率
・「申し込み制」の場合(自分で加入手続きが必要):加入率25%
・「自動加入」の場合(辞めたい人だけ手続き):加入率85%
内容は同じでも、初期設定を変えるだけで結果が劇的に変わるのです。
✅ 対策:『先取り貯蓄』をデフォルトにする
この性質を逆手に取りましょう。給料が入ったら、考える前に自動的に一定額が積立投資に回る「先取り貯蓄」を設定するのです。一度設定してしまえば、あとは脳の省エネ本能が「何もしない」ことを選び、勝手にお金が貯まる仕組みが完成します。
罠2:未来の価値を割り引く「時間割引」
人間は、遠い未来の大きなメリットよりも、目先の小さなメリットを過大評価するクセがあります。これを時間割引と呼びます。
「今すぐもらえる1万円」と「明日もらえる1万100円」なら、多くの人が前者を選びます。
しかし、「1年後にもらえる1万円」と「1年と1日後にもらえる1万100円」なら、後者を選ぶ人が増えるのです。
この思考のクセが、長期投資の最大の敵です。「将来のため」と分かっていても、つい目先の消費や誘惑に負けてしまうのは、この「時間割引」が強力に働いているからです。
✅ 対策:未来の価値を「見える化」する
将来のメリットが曖昧だから、価値を感じられないのです。ならば、具体的なシミュレーションで「見える化」しましょう。「毎月5万円を30年間積み立てると、これだけの金額になる」という具体的な数字を見ることで、脳は「今5万円を投資する価値がある」と納得しやすくなります。
罠3:損失を極端に恐れる「プロスペクト理論」
これは行動経済学で最も有名な理論の一つですが、人間は「利益を得る喜び」よりも「損失を被る苦痛」を2倍以上も強く感じるという性質です。
「5万円儲かります」と言われるより、「このままだと5万円損します」と言われた方が、人は行動を起こします。この心理が、投資で最悪の判断「狼狽売り」を引き起こします。
株価が暴落した時、「これ以上損したくない!」という強烈な苦痛から、本来なら持ち続けるべき優良な資産を底値で手放してしまうのです。
✅ 対策:損失はチャンスの裏返しだと知る
歴史的に見て、株価が大きくマイナスになった年の翌年は、非常に高いリターンが期待できることが繰り返されています。「損失の苦痛」に耐え、冷静に持ち続ける、あるいは買い増すことができれば、その苦痛以上の恩恵を受けられることを、知識として知っておくことが最大の防御になります。
罠4:過去のコストに縛られる「サンクコスト効果」
「ここまでお金や時間をかけたんだから、今さらやめるのはもったいない」と感じてしまう心理、これがサンクコスト(埋没費用)効果です。
私が相談現場で最もこの罠を感じるのが、貯蓄型の保険です。
「この保険、あと10年続ければ元本は戻ってきます。でも今解約すると100万円損します…」
この状況で、多くの人が「100万円損するのはもったいない」と考え、非効率な保険を続けてしまいます。しかし、合理的に考えれば、今100万円損したとしても、これから払うはずだったお金をインデックスファンドなどに回せば、トータルではるかに大きな利益を得られる可能性が高いのです。
✅ 対策:判断基準を「未来」に置く
サンクコストの罠を断ち切るには、「これからどうするのが、将来の自分にとって最もメリットがあるか?」という一点だけで判断することです。過去にいくら払ったかは、未来の判断には一切関係ありません。その事実を意識するだけで、合理的な決断ができるようになります。
まとめ:自分の「脳のクセ」を知り、賢く付き合うことが富への第一歩
今回は、お金に困る人が無意識にハマってしまう4つの思考の罠を、行動経済学の観点から解説しました。
- デフォルト効果:面倒だからと初期設定に従う → 対策:良い習慣を「デフォルト」に設定する(先取り貯蓄など)
- 時間割引:未来の価値より目先の快楽を優先する → 対策:未来の価値をシミュレーションで「見える化」する
- プロスペクト理論:利益より損失の痛みを強く感じる → 対策:損失の局面こそチャンスだと「知識」で理解する
- サンクコスト効果:過去のコストがもったいなくてやめられない → 対策:判断基準を常に「未来」に置く
重要なのは、これらの思考のクセは、人間である以上誰にでもあるということです。
大切なのは、「自分にはこういうクセがあるんだ」と自覚し、重要な判断をする時だけ意識的に立ち止まって、合理的な視点で考えることです。
自分の脳を理解し、賢く手なずけること。それこそが、10年後にお金に困らない人生を送るための、最も確実な第一歩なのです。
あなたの投資判断を「なんとなく」から「確信」へ変えませんか?
「今日の株価変動の本当の理由は?」「この相場で、自分の長期戦略は正しいのだろうか?」
そんな疑問や不安に、プロの分析でお答えします。
今、LINEに登録いただいた方限定で、以下の情報を凝縮した
限定PDFレポートを【2週間に1回、無料】で継続的にお届けしています。
- リアルタイムの株価変動:その「なぜ?」を深掘り分析
- 長期投資家が知るべき、最新のマーケット考察
- あなたの資産効率を上げる、具体的なヒントと戦略
長期投資家にとって、資産効率をさらに高めるヒントが満載です。

赤坂ファイナンシャル株式会社 代表取締役
元大手企業勤務、3,000人以上の相談実績と著書『地味な投資で2000万円』を持つお金のプロ。ファイナンシャルプランナー、クレジットカードアドバイザー®として、難しい金融の話を初心者向けにわかりやすく解説しています。
主な実績
著書:『自由に生きるための 地味な投資で2000万円』
メディア出演:テレビ朝日「グッド!モーニング」、週刊SPA!、現代ビジネス、プレジデントオンライン等 多数
講演実績:一部上場企業、経営者団体など