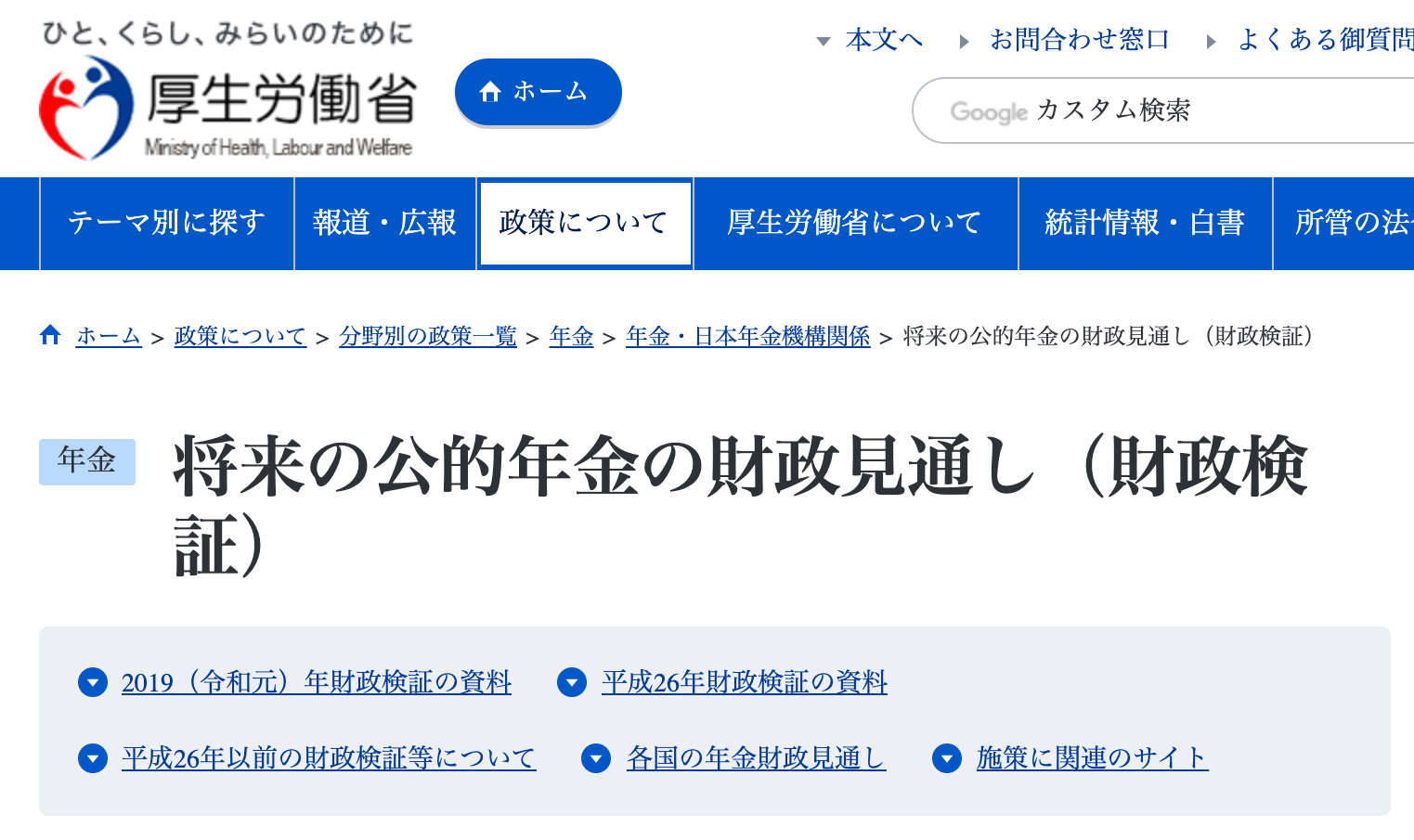終身雇用は崩壊、年金だけでは暮らせない。40代から始める「生涯現役」時代の働き方と資産形成
「このままで、老後は本当に大丈夫だろうか…」
40代・50代を迎え、会社の役職や子どもの成長など、ライフステージが大きく変化する中で、漠然とした不安を感じていませんか?
かつての日本社会の常識だった「終身雇用」「退職金」「豊かな年金」という3つの柱は、今や崩壊しつつあります。「60歳で定年し、悠々自適な老後」というモデルは、もはや幻想となりました。
【40代・50代のあなたへ】
「生涯現役」という言葉は、もはや他人事ではありません。これは、国や会社に頼らず、自らの力で人生の後半戦を生き抜くことが求められる時代の始まりを意味します。しかし、悲観する必要はありません。経験と知識が豊富な40代・50代の「今」だからこそ、打てる手は数多くあります。
この記事では、私たちが直面する厳しい現実をデータで直視し、これからの時代を生き抜くための具体的な「働き方」と「資産形成」の戦略を、専門家の視点から徹底解説します。
40代・50代が直面する「3つの逃れられない現実」
現実①:「定年」というゴールの消滅
2021年4月に施行された「改正高年齢者雇用安定法」により、企業には70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。しかし、多くの企業が採用する「再雇用制度」では、60歳以降の給与が現役時代の5〜7割に減少するケースがほとんど。「60歳でゴール」ではなく、「60歳から収入が激減した状態で働き続ける」のが現実です。
現実②:「健康寿命」と「平均寿命」の残酷な差
最新のデータ(2022年発表)によると、日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳です。しかし、自立して健康に生活できる期間を示す「健康寿命」は、男性72.68歳、女性75.38歳。つまり、平均で9年〜12年間は、介護や医療の助けが必要な期間が続く可能性があるのです。この期間の生活費や医療・介護費は、年金だけで賄えるでしょうか?
現実③:減らない「支出」と増えない「収入」
40代・50代は、子どもの教育費や住宅ローンに加え、親の介護費用が重くのしかかる「ダブルケア」の時代でもあります。支出が増え続ける一方で、日本全体の賃金は30年間ほぼ横ばい。会社の給料だけに頼る一本足打法では、家計が立ち行かなくなるリスクが高まっています。
【戦略①】40代から始める「働き方」の再設計
「生涯現役」時代を乗り切るには、会社に依存した働き方から脱却し、自らの市場価値を高め、収入源を複数持つ「複業」の発想が不可欠です。
ステップ1:リスキリング(学び直し)で市場価値を高める
今の会社でしか通用しないスキルになっていませんか?これまでの経験を活かしつつ、AI、データ分析、Webマーケティング、プログラミングといった、今後需要が高まる分野のスキルを学び直す(リスキリング)ことで、社内での価値を高めるだけでなく、転職や独立の道も開けます。
ステップ2:「複業(複数の本業)」で収入源を増やす
お小遣い稼ぎの「副業」ではなく、これまでのキャリアで培った専門知識や経験を活かし、コンサルティングやアドバイザー、研修講師といった形で、複数の企業や個人と関わるのが「複業」です。単なる労働時間の切り売りではなく、あなた自身の価値を収入に変える働き方を目指しましょう。
【戦略②】40代から始める「資産形成」の加速
働き方を見直すと同時に、お金にも働いてもらう「資産形成」を加速させることが、経済的自立へのもう一つの重要な柱です。
なぜ40代・50代が「最後のチャンス」なのか?
資産形成は、「投資額 × 運用期間」で成果が決まります。退職までの期間が20年、10年と短くなるこの世代は、残された「運用期間」を最大限に活かす必要があります。収入がピークに達する今こそ、NISAやiDeCoといった制度をフル活用し、老後資金作りのラストスパートをかけるべき絶好のタイミングなのです。
ステップ1:新NISAとiDeCoを「最優先」で満額利用する
国が用意してくれた最も有利な「武器」を使わない手はありません。運用益が非課税になるNISA、掛金が所得控除になるiDeCo。この2つの制度を、他のどんな金融商品よりも優先し、可能な限り上限額まで活用することが、資産形成の王道にして最短ルートです。
ステップ2:退職金を「守りながら増やす」計画を立てる
数年後に受け取る退職金は、老後の命綱です。しかし、それを金利0%の銀行に眠らせておけば、インフレで価値が目減りするだけ。退職金を受け取った際に慌てて投資で失敗しないよう、「どのくらいを生活防衛資金とし、どのくらいをNISAなどで運用に回すか」という計画を、今のうちから立てておくことが極めて重要です。
結論:「生涯現役」を、最高の人生後半戦に変えるために
「生涯現役」と聞くと、ネガティブなイメージを持つかもしれません。しかし、見方を変えれば、それは会社や年齢に縛られず、自らの意志で働き方や生き方を選択できる「自己実現の時代」の到来とも言えます。
その自由を手に入れるために不可欠なのが、経済的な基盤です。40代・50代の今、自らの「稼ぐ力」と「増やす力」に本気で向き合うこと。それが、不安な未来を、希望に満ちた最高の人生後半戦に変えるための、唯一の鍵なのです。
▶︎ 実際の年金受給額データも参考に、より具体的なイメージを掴んでみてください。
→会社員の年金受給額はいくらくらいなのか?【実際のデータを公開】

赤坂ファイナンシャル株式会社 代表取締役
元大手企業勤務、3,000人以上の相談実績と著書『地味な投資で2000万円』を持つお金のプロ。ファイナンシャルプランナー、クレジットカードアドバイザー®として、難しい金融の話を初心者向けにわかりやすく解説しています。
主な実績
著書:『自由に生きるための 地味な投資で2000万円』
メディア出演:テレビ朝日「グッド!モーニング」、週刊SPA!、現代ビジネス、プレジデントオンライン等 多数
講演実績:一部上場企業、経営者団体など