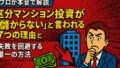親が遺してくれた、大切な実家。それは家族にとってかけがえのない“資産”のはずでした。しかし、その一つの不動産が引き金となり、あれほど仲の良かった兄弟姉妹の関係に、深い亀裂が入ってしまう…。
こんにちは。3000件以上の資産相談、特にこうしたデリケートな相続問題に数多く向き合ってきた、ファイナンシャルプランナーのまさとFPです。「相続」が骨肉の争いを意味する「争族」になってしまう悲劇を、私は何度も目の当たりにしてきました。
その原因のほとんどは、不動産相続に潜む「隠れコスト」と、コミュニケーション不足にあります。
この記事では、あなたがそんな悲劇の当事者にならないために、相続で本当に必要なお金の知識と、家族の絆を守るための具体的な知恵を、余すことなくお伝えします。親御さんが遺した本当の想いを、円満な形で未来へ繋ぐための一助となれば幸いです。
相続はプラスの財産”だけじゃない?「隠れコスト」の恐ろしい正体
不動産を相続すると聞くと、「家が手に入る」というプラスの面ばかりを想像しがちです。しかし、実際には、目に見えない様々なコストが同時に発生します。これを知らないと、後で「こんなはずでは…」と資金繰りに窮することになります。
目に見える財産(プラス)
土地・建物そのもの
↓
資産価値
(例:3,000万円)
隠れコスト(マイナス)
相続税
登録免許税
不動産取得税
専門家への報酬
固定資産税
維持管理費…etc
まずは、どのような税金が、いつ、どのくらいかかるのか。その全体像を把握しましょう。
【税金の全貌】不動産相続でかかる“可能性がある”3つの税金
①相続税:そもそも、うちは払う必要がある?
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。遺産総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、課税されます。
【FPの視点】
例えば、相続人が妻と子供2人(合計3人)の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円×3人)となります。実家の評価額や預貯金などを合わせた遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。まずは、ご自身の家庭が課税対象になるのか、この計算式で確認することが第一歩です。
②登録免許税:不動産の名義変更にかかる税金
相続した不動産を、亡くなった親の名義から自分の名義に変更(相続登記)する際に、法務局に納める税金です。これは、相続税がかからない場合でも必ず発生します。
【FPの視点】
例えば、評価額2,000万円の不動産なら、8万円の登録免許税がかかります。司法書士に手続きを依頼する場合は、別途5〜10万円程度の報酬が必要になります。
③不動産取得税:原則かからないが“例外”に注意
不動産を取得した際にかかる税金ですが、法定相続人が相続で取得した場合は、原則として非課税です。ほとんどのケースで心配は不要です。
【FPの視点】
ただし、遺言によって相続人以外の人(孫や内縁の妻など)が不動産を取得(遺贈)した場合は、課税対象となるため注意が必要です。
プロが実践する相続税対策|手残りを最大化する“3種の神器”
もし相続税の課税対象になったとしても、ご安心ください。正しく活用すれば、納税額をゼロにできる可能性もある、強力な特例が存在します。
亡くなった方が住んでいた土地などを相続した場合、その土地の評価額を最大で80%も減額できる、最もパワフルな特例です。例えば、5,000万円の土地の評価額が1,000万円になり、相続税を劇的に圧縮できます。配偶者や同居していた親族が相続する場合などに適用できます。
亡くなった方の配偶者が遺産を相続する場合、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないという特例です。ほとんどのケースで、配偶者が相続する分には相続税はかからないと考えてよいでしょう。ただし、二次相続(その配偶者が亡くなった時の相続)で子供たちの負担が重くなる可能性も考慮が必要です。
これは生前対策ですが、被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた生命保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税になります。相続財産が現金ではなく不動産に偏っている場合、この非課税枠を使って納税資金や手続き費用を準備しておくのは、非常に賢い方法です。
「争族」を回避するFPの知恵|家族の絆を守る“3つの絶対ルール”
お金の問題以上に深刻なのが、家族関係の崩壊です。それを防ぐために、FPとして必ずお伝えしている3つのルールがあります。
なぜ争いが起きるのか?それは、そこに明確なルールがないからです。「誰に何を遺すか」という親の意思を記した遺言書は、残された家族が迷わないための最高の道しるべです。財産の話は切り出しにくいものですが、「家族が揉めないために」という想いを伝え、作成を促すことが子の務めでもあります。
「親の財産がどれだけあるか誰も知らない」という状況が、疑心暗鬼を生みます。親が元気なうちに、不動産だけでなく預貯金や有価証券、借金も含めた財産の一覧表(エンディングノートなど)を作成してもらい、家族全員で情報を共有する場を設けましょう。透明性が、信頼の土台となります。
実家を兄弟で平等に分けるため、「2分の1ずつ」といった共有名義にするのは、最悪の選択の一つです。将来、その不動産を売却・活用する際に、共有者全員の同意が必要となり、身動きが取れなくなります。さらに、その子供たちの代に相続が発生すると、権利関係はネズミ算式に複雑化します。相続の際に、誰が不動産を取得するのか、代償金(不動産をもらう代わりに他の相続人にお金を払う)をどうするかなど、必ず一代で解決させましょう。
まとめ:最高の相続とは、家族の“円満”を引き継ぐこと
不動産の相続は、単なる手続きではありません。それは、親から子へ、そして次の世代へと、家族の歴史と想いを引き継ぐ大切な儀式です。
そのためには、お金の知識(税金対策)と、心の準備(家族の対話)の両輪が不可欠です。この記事でご紹介した「隠れコスト」と「3つのルール」を道しるべに、ぜひご家族で話し合うきっかけを作ってください。それが、親御さんが本当に望んでいる、最高の親孝行かもしれません。
相続の不安、一人で抱え込んでいませんか?
今、公式LINEに友だち登録していただくと、限定特典
【知識ゼロから始める】不動産投資スタートアップ・バイブル(PDF)
を無料でプレゼント!
「うちの場合、相続税はかかる?」「兄弟と揉めない分け方は?」そんなデリケートなご質問にも、3000件以上の相談実績を持つFPが、あなたの家族に寄り添いながら最適な解決策をご提案します。

赤坂ファイナンシャル株式会社 代表取締役
元大手企業勤務、3,000人以上の相談実績と著書『地味な投資で2000万円』を持つお金のプロ。ファイナンシャルプランナー、クレジットカードアドバイザー®として、難しい金融の話を初心者向けにわかりやすく解説しています。
主な実績
著書:『自由に生きるための 地味な投資で2000万円』
メディア出演:テレビ朝日「グッド!モーニング」、週刊SPA!、現代ビジネス、プレジデントオンライン等 多数
講演実績:一部上場企業、経営者団体など