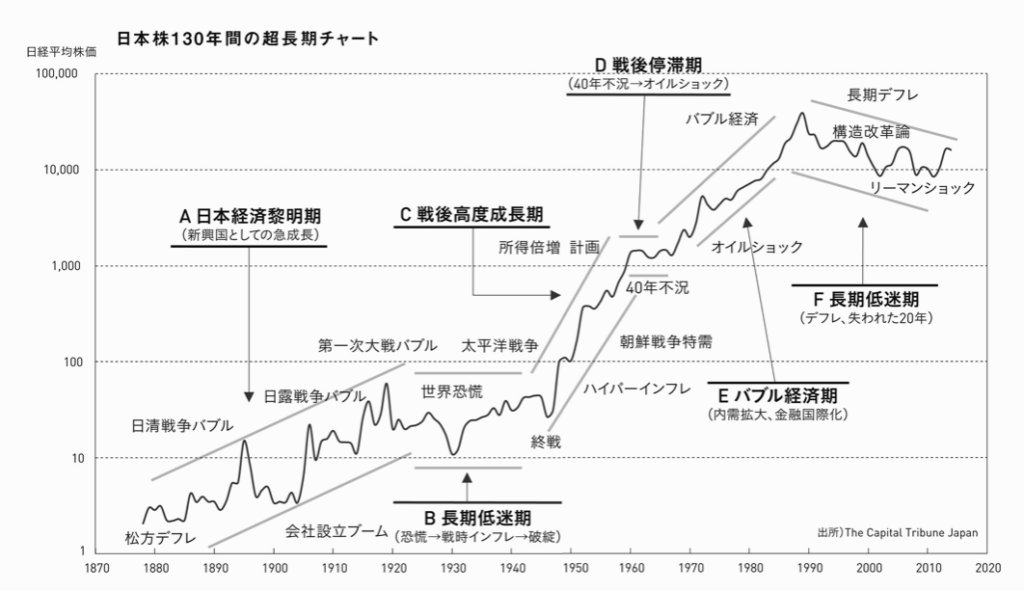金本位制とは、金をお金の価値の基準とする制度です。
政府の銀行が、発行した紙幣と同額の金を保管しておき、いつでも金と紙幣を交換することができる制度で、19世紀から20世紀のはじめにかけて、世界各国で取り入れられていました。
しかし経済の仕組みが変わるにつれ、金本位制は次第に崩れ、1930年代には、ほとんどの国で廃止されてしまいました。
代わって登場したのが管理通貨制度です。この制度は、金の保有量とは無関係に法律で定められた通貨制度に基づいて、その国の中央銀行、日本では日本銀行が貨幣の量を管理する制度です。
金本位制は、保有する金の量によって、発行する貨幣が制限されますが、管理通貨制度では、国の信用によってお金の価値が決まります。
現在、世界各地の為替市場で、世界中の貨幣が取引されています。
それぞれの国の貨幣の値打ちは、そこで決まります。
国の経済への信頼がなくなれば、貨幣の価値も下がってしまうのです。